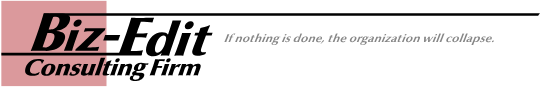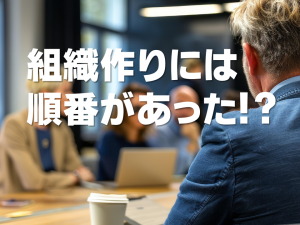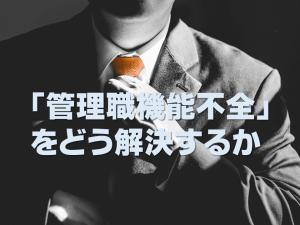パート比率8割の組織に未来はあるか? 拡大前の人材戦略を考える
先日、ある地方の事業者から相談を受けました。
業績はようやく黒字化。赤字体質から抜け出し、今期も見込みは悪くない。自治体からも「地域の需要に応えるため、施設を増やせないか」と声がかかるほど。いよいよ次のステージ、というわけです。
社長も前向き。2,000万円の設備投資を視野に、金融機関とも話を進めている。収支計画書の提出も済ませ、資金面のメドは立ちつつある——
と、ここまでは「よくある成功ストーリー」のように見えます。
けれど、私の目にまず飛び込んできたのは、**「組織」の状態**でした。
従業員は20人余り。その8割以上がパートタイマー。正社員は数人のみ。評価制度はなく、業務分担の定義も曖昧。さらに、いわゆる「主任」や「リーダー」の役割を担うのは、年齢が上のパート社員たち。もちろん、形式的な昇格やトレーニングはない。
もしこの状態で規模だけが大きくなったら……
はっきり言います。**たぶん、壊れます**。
パート主体の組織で事業を拡大するリスクとは
一見、パート比率が高いこと自体は悪ではありません。業態や事業モデルによっては、非常に機能することもあります。ただし、問題はその組織が**「拡大に耐えうる構造」**を持っているかどうか、です。
「売上が伸びているのに、人が辞めていく」
「新しい人を入れても、すぐ辞める」
「誰が何をやるかが曖昧で、責任のなすり合いになる」
そんな未来が、静かに、しかし確実に近づいているかもしれません。
よくある“拡大の落とし穴”にハマらないために
中小企業の多くは「人の問題」に対して後手に回りがちです。
理由はシンプル。**そもそも“組織を設計する”という発想がないから**。
たとえば、実力よりも「勤務年数」で昇進させてしまう。
「なんとなく頼りになるから」という理由でリーダーに任命する。
それ自体は責められることではありません。でも、それを制度として支える枠組みがなければ、リーダー本人も苦しくなります。そして、組織全体が“空気で動く集団”になっていきます。
これが、拡大を阻む最大のボトルネックです。
組織づくりは“後”ではなく“前”にするもの
ここで私が提供しているのが、**「組織の見える化」から始まる支援**です。
・現場スタッフの業務分解
・役割と権限の再定義
・評価制度の簡易設計
・経営層と現場の“翻訳”支援
・そして、現場を支えるリーダーの育成
「とりあえず投資してから考える」では間に合いません。
**“人”の準備は、拡大を始める前に終えておくべきです。**
まとめ:成長のタイミングこそ“人”を見るべき理由
事業の成長は、社長にとって嬉しいニュースです。金融機関も自治体も、口を揃えて「今がチャンス」と言ってくる。けれどその声に押され、組織の準備を後回しにすると、後から必ずツケが来ます。
私たちはつい、「数字が見える」ものを優先して判断してしまいがちです。
でも、「見えにくい“人”の準備」こそが、長期的な成功を左右します。
組織コンサルタントに相談するという選択肢
私は、全国対応でスポット契約型の組織コンサルティングを行っています。
定期的な顧問契約ではなく、必要なタイミングで、必要なだけ支援する柔軟なスタイルです。
「組織をどう作ればいいのか、何から手をつけていいかわからない」
そんなときこそ、お気軽にご相談ください。
ご質問・ご相談はこちらからどうぞ。
まずは一度、組織の現在地を一緒に“見える化”してみませんか?